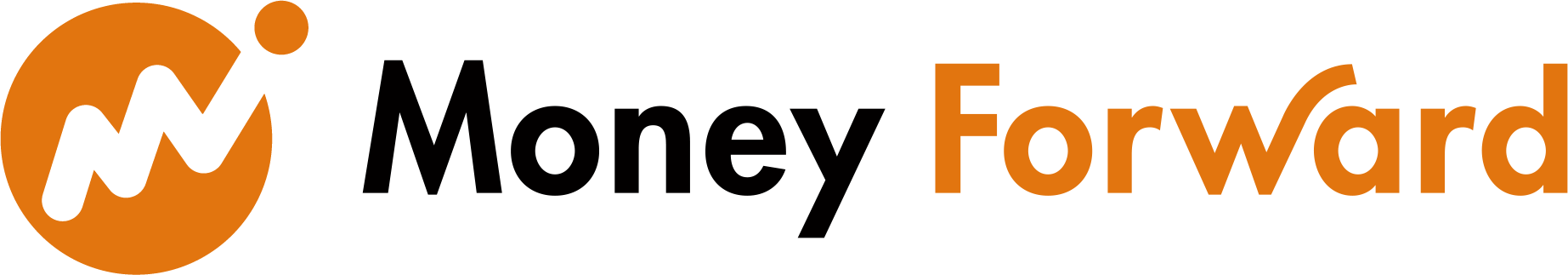|
|
|||

|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
子供のマネー教育は、親子で楽しむ「あつまれ どうぶつの森」 |
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
一般的なサラリーマンでありながら、40代で億単位の資産を築かれたKさん。 |
|||
|
|
|||
|
お子さまにお小遣いはあげていますか? |
|||
|
|
|||
|
小学生の子供が2人いますが、お小遣いはあげていません。欲しいものがある場合は、誕生日やクリスマスといったイベント時にのみ買ってあげます。あとは、お風呂掃除などのお手伝いをしたら、週末に好きなお菓子を買ってあげたりというくらいですかね。深い考えはありませんが、奥さんがちょこちょこ買ってあげたりしないタイプなのでそのようになっています。 |
|||
|
|
|||
|
マネー教育として、お子さまにはどのようなことを教えてらっしゃるのですか? |
|||
|
|
|||
|
きちんとしたマネー教育を何かしているわけではありませんが、「あつまれ どうぶつの森」は貯金や投資といった考え方を学ぶのに良いゲームだなと感じています。 |
|||
|
|
|||
|
ゲームを通して、現実世界での学びにもつながりそうでしょうか? |
|||
|
|
|||
|
けっこう現実と近しいというか、性格が現れるんですよ。私は、ゲームの中でもお金を増やしています(笑)採った虫を、普通のお店より高く買ってくれる人に売るとか。お金を増やすことばっかりしていて、気付いたらお金持ちになっていました。銀行みたいな家を作って、金庫のような壁紙にして防犯カメラつけたりすることを楽しんでいます。 |
|||
|
|
|||
|
|
|||
|